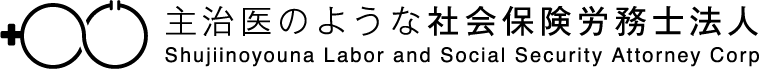なぜ、一人の芸術家が、これほどまでに街の人々に愛され、深く尊敬されるのだろうか。
社会保険労務士として日々、組織や個人の「働く」というテーマに向き合う中で、私の胸にはある問いが静かに浮かんでいました。ルールや効率、数字で測れる成果が優先される現代の日本で、私たちは本当に大切なもの、人間の営みの根底にあるべき「本質」を見失ってはいないだろうか、と。
その答えのヒントを探すように、私はイタリアへと旅立ちました。
目的は、単なる観光ではありません。歴史的建造物が現代のビジネスとして息づく街々を巡り、日本の労働慣行やまちづくりのあり方を違う視点から見つめ直すこと。そして何より、かの地で「マエストロ」と呼ばれる本物の職人魂に触れ、私自身の根底にある価値観を、より確かなものにすること。
これは、水の都ベネツィアから始まり、芸術の都フィレンツェを経て、大理石の街ピエトラサンタでの魂を揺さぶる出会いに至り、そしてミラノで未来への思索にふけるまでを綴った、私の探求の物語である。

歴史が息づく街々。ベネツィアとフィレンツェ
旅の始まりは、ベネツィア。そこは、車輪の音が一切しない街だった。
地上を走る自動車が存在せず、人々の足となるのはヴァポレットと呼ばれる水上バスやゴンドラ。一枚の乗り放題チケットを手に、迷路のような水路を巡れば、この街の常識が、いかに私たちの日常と違うかを肌で感じさせられる。交通インフラさえもが、中世から続く街の骨格を尊重するように設計されているのだ。

街並みに目を向ければ、その思想はさらに色濃く現れる。歴史を重ねた荘厳な建物が、当たり前のように高級ホテルやブティックとして息づき、現代のビジネスの舞台となっている。日本では「古い=価値が低い」と見なされ、次々と新しいものに建て替えられていく光景が珍しくない。「スクラップ&ビルド」を繰り返し、建てること自体が目的化するフロー型の社会。それに対し、彼らは今あるものをどう活かし、未来へ繋ぐかを考えるストック型の思想が根付いている。
古い教会は、その荘厳さを保ったまま美術館となり、人々の感性を潤す。建物に刻まれた記憶や物語を、次の世代へと丁寧に受け継いでいく文化。日本もまた、真に価値ある建築物を長く使い、歴史を誇りとして刻んでいく社会へと成熟できないだろうか。ベネツィアの風景は、私に静かな、しかし重い問いを投げかけていた。

次に訪れたフィレンツェでも、その想いは確信に変わる。アルノ川に架かるヴェッキオ橋の上には、きらびやかな宝石店や土産物屋が軒を連ね、橋の上でさえ人々の営みが溢れ出している。歴史そのものが、生活の一部として溶け込んでいるのだ。
歴史を未来に繋ぐ思想。それは、ただ建物を残すことだけではないはずだ。
その思想を、自らの手で、生き様で体現する者たち。人々が「マエストロ」と呼ぶ職人たちに会えば、もっと深い答えが見つかるかもしれない。
期待を胸に、私は旅の核心、ピエトラサンタへと向かった。

ピエトラサンタで出会った「マエストロ」の魂
旅の核心、ピエトラサンタ。ミケランジェロも愛したという白亜の大理石の産地であり、世界中の芸術家が集うこの街で、私は生涯忘れられない光景と出会うことになる。
目的は、世界的な彫刻家・安田侃氏の野外彫刻展「OLTRE LA FORMA 形を超えて」の鑑賞。街の中心広場や教会に点在する氏の作品群は、それ自体が圧倒的な存在感を放っていた。しかし、私の心を本当に揺さぶったのは、作品そのもの以上に、作品と人々との関わり方だった。

日本の美術館にある「お手を触れないでください」という注意書きが、ここではまるで別世界のルールだ。子供たちは大理石の滑らかな曲線によじ登り、恋人たちは彫刻に腰掛けて語らい、ある人は作品に身を預け、穏やかに寝転んでいる。アートが「鑑賞」するものではなく、人々の生活に、魂に、深く溶け込んでいるのだ。日本、そしてここイタリアでも、安田侃氏の作品がこれほどまでに愛されているという事実に、ただただ胸が熱くなった。

その感動は、街を歩いているときに頂点に達した。
安田氏と共にランチへと向かう、何気ない昼下がり。突如、道端の店先から、市場の店主から、次々と温かい声が飛んでくる。
「マエストロ!」「ボンジョルノ、マエストロ!」 彼らが向けるのは、単なる有名人への好奇の視線ではない。心からの「尊敬の眼差し」そのものだった。作品はもとより、安田侃という人間の存在そのものが、この街の誇りなのだ。日本では氏の作品を知る人は多くとも、これほどまでに作り手自身が街と一体化しているだろうか。いや、ないだろう。

この時、私はタイトルの問いの答えを見つけた気がした。 巨匠が街に愛されるのは、彼らが単に美しいものを作るからではない。その哲学、生き様、そして作品を通して街に与えるインスピレーションのすべてが、人々の血肉となっているからだ。これこそが文化の成熟であり、「本物」が持つ力なのだと、全身で理解した。
安田侃財団の理事として、この光景を目の当たりにできたことは、私の人生にとって大きな財産だ。世界的な巨匠の仕事に携われる誇りを胸に、この感動を原動力として、財団の活動に一層力を尽くしていきたい。私の心は、確かな決意で満たされていた。

ミラノの夜に想う。旅の終わりと、新たな始まり
旅の終着点、ミラノ。街中のホテルのバルコニーで、最後の夜を迎えた。
眼下には、トラムや車が絶え間なく行き交い、ミラノ大学の学生たちの楽しげな声が響いてくる。ピエトラサンタの静謐な空気とは違う、最先端の都市が放つ活気とエネルギー。私はそれを、どこか穏やかな気持ちで眺めていた。
荘厳なドゥオーモ、歴史的建造物を改装したPRADA本店。この街でもまた、歴史とビジネスが鮮やかに共存している。しかし、私の脳裏に焼き付いて離れないのは、やはりピエトラサンタのあの光景だった。
これから日本に戻り、また社会保険労務士としての日々が始まる。この旅で何かが劇的に変わるわけではないかもしれない。だが、私の内側には、確かな一本の芯が通ったように思う。小手先のテクニックや効率だけではない、物事の「本質」を見つめる視点。それを忘れずにいたい。
本物の価値観を持てるように、これからも様々な活動を通じて学び、探求し続けていきたい。バルコニーを吹き抜ける夜風を感じながら、私は静かにそう決意した。
旅を終えた今、私の手の中に、問いに対する明確な言葉があるわけではないのかもしれない。
ただ、ピエトラサンタの石畳の感触と、マエストロに向けられた人々の温かな眼差しが、これから私が進むべき道を、静かに照らしてくれている。
この旅の物語から、あなたが何かを感じ取ってくださったなら、それ以上に嬉しいことはない。